短期矯正で保険適用されるケースとは?手順と費用を抑えるコツも解説

短期間で歯並びを整える「短期矯正」は、見た目の改善を目的とした自由診療のイメージがあります。
しかし、特定の疾患や症例に該当する場合、健康保険が適用されることがあるため、適用条件を正しく理解することが大切です。
制度を知らないまま治療を始めてしまうと、本来なら保険を利用できるケースでも、全額自己負担となるおそれがあります。
条件や手続きの流れを把握しておけば、費用を大きく抑えながら、安心して治療を進められるでしょう。
この記事では、短期矯正で保険が適用される具体的なケースや診断の流れ、さらに費用を抑えるための工夫を整理しました。
矯正歯科を検討している方や、費用面で無理なく治療を受けたい方は、参考にしてください。
短期矯正で保険適用される5つのケース
短期矯正が保険の対象となるのは、見た目の改善ではなく機能回復を目的とした場合です。
適用範囲を正しく把握しておくことで、自己負担を最小限に抑えた治療を受けられます。
ここでは、保険適用されるおもな例を5つ紹介します。
- ・先天的な異常による咬合不全
- ・事故や外傷による歯列・顎の異常
- ・顎変形症を伴う治療
- ・口唇裂や口蓋裂に関わる不正咬合
- ・重度の咀嚼障害や発音障害の治療
ご自身の症状と照らし合わせて検討してください。
先天的な異常による咬合不全
生まれつき歯や顎の形に異常がある場合、噛み合わせに深刻な支障をきたすことがあります。
たとえば歯の欠如や過剰歯、歯の位置異常が重度で、咀嚼が難しいケースです。
これらは単に見た目に問題があるだけでなく、成長や発音、日常生活に大きな影響を及ぼすため、保険適用の対象です。
治療のタイミングによっては、矯正だけでなく外科的処置を併用する場合もあります。
なお、該当する先天性疾患は、厚生労働省により保険適用疾患として定められています。
事故や外傷による歯列・顎の異常
外傷による顎の骨折や変形、歯の欠損などが、咀嚼や発音に深刻な影響を及ぼす場合は、保険適用の対象に含まれる可能性があります。
交通事故や転倒などによって、歯列や顎の骨が損傷し、正常な噛み合わせを維持できないといったケースです。
ただし、矯正治療単独ではなく、外科手術や口腔外科での治療と併用されるケースに限られるのが一般的です。
とくに若年層では成長発育への悪影響も考えられるため、早期に専門機関で診断を受けましょう。
顎変形症を伴う治療
顎変形症は、上下の顎の位置や大きさに著しい不調和が生じ、噛み合わせや顔貌に大きな影響を与える疾患です。
重度の場合は咀嚼が困難になったり、発音が不明瞭になったりするため、健康保険の適用対象に含まれます。
ただし、保険が認められるのは矯正治療に加え、外科的手術(顎矯正手術)と矯正治療を併用する場合です。
治療は長期的な管理を要することも多いため、早めに矯正歯科や口腔外科など専門の医療機関で診断を受けることが重要です。
口唇裂や口蓋裂に関わる不正咬合
口唇裂は上唇が生まれつき裂けている状態、口蓋裂は口の天井部分(口蓋)に裂け目がある状態を指します。
これらはいずれも「唇顎口蓋裂」と総称され、歯の萌出や顎の発育に大きな影響を及ぼし、噛み合わせに不具合が生じやすい疾患です。
病状によっては、発音が不明瞭になるだけでなく、食べ物や飲み物が鼻へ漏れることも。
長期にわたり、外科手術や言語訓練など、多職種の連携治療が行われるケースもあります。
重度の咀嚼障害や発音障害の治療
咀嚼障害は、硬いものが食べられなかったり、食事時間が極端に長くなったりといった、食べ物を十分に噛み砕けない状態を指します。
また、発音障害は、舌や歯の位置が原因で言葉が不明瞭になるもので、とくに「サ行」や「タ行」が聞き取りにくいのが代表的な症状です。
ただし、これらの症状があるからといって、自動的に保険が適用されるわけではありません。
厚生労働省が指定する疾患に起因する場合に限り、機能改善を目的とした矯正治療が保険適用の対象です。
短期矯正で保険適用を受ける5つの手順
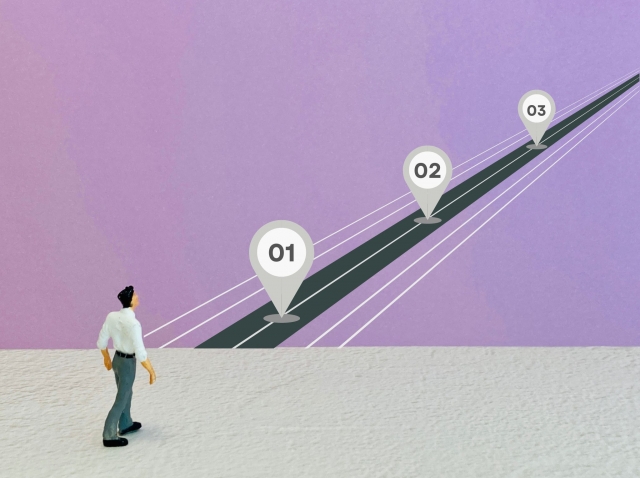
短期矯正で健康保険を利用するには、特定の流れに沿って進めることが必要です。
単に「対象となるかどうか」を確認するだけでなく、診断や申請、治療後の支払いまで段階的に手続きが設けられています。
ここでは、保険適用を受ける5つの手順を解説します。
- 1.歯科医院で診断し、治療計画を立てる
- 2.保険適用の対象かどうか確認する
- 3.医療機関で書類を作成し、申請する
- 4.矯正治療を開始し、経過を観察する
- 5.保険適用に基づいた費用で支払う
順に見ていきましょう。
1.歯科医院で診断し、治療計画を立てる
最初の手順は、歯科医院で詳細な診断を受けることです。
口腔内の状態を確認するために、レントゲン撮影や歯型の採取、顎の動きや咬合のチェックなどを行います。
これらの情報をもとに、治療の必要性や方法、期間を含めた計画が立てられます。
とくに短期矯正の場合、部分的な処置で対応できるのか、全体的な矯正が必要なのかを見極めることが大切です。
この段階での診断結果は、その後に保険適用が認められるかどうかの判断材料となり、医療機関が保険請求する際の基礎資料として使われます。
2.保険適用の対象かどうか確認する
診断が終わったら、その結果が厚生労働省の定める保険適用条件に該当するかどうかを確認します。
適用対象は、前述した唇顎口蓋裂などの先天的な異常や顎変形症、外傷による歯列不正など、機能回復を目的とした矯正治療に限られます。
一方、審美目的の矯正や軽度の歯並び改善は対象外です。
この判断は、指定自立支援医療機関として認定された歯科医師が行い、必要に応じて大学病院や専門機関と連携して、確認される場合もあります。
早い段階で適用の可否を把握しておくことで、費用の見通しが立ちやすく、安心して治療を検討できます。
3.医療機関で書類を作成し、保険請求を行う
保険適用が見込まれる場合、医療機関に書類を作成してもらいます。
診断書や治療計画書、X線画像などの資料が準備され、これらをもとに医療機関が保険者へ診療報酬を請求します。
患者自身が申請手続きを行う必要はなく、指定自立支援医療機関として認可を受けた歯科医院や大学病院が対応するのが基本です。
必要な書類や記載内容が不十分だと、保険適用が認められない場合があるため、専門医の管理のもとで正確に進めることが重要です。
4.矯正治療を開始し、経過を観察する
保険適用が認められたあと、いよいよ矯正治療が始まります。
治療中は装置の調整や歯の移動具合、顎の動きの確認などを行うため、定期的な通院が欠かせません。
短期矯正の場合でも、効果を最大限にするには細かなチェックが不可欠です。
治療中は、装置による口腔内の違和感や、歯周環境の変化が見られることもあるため、異変を感じたら早めに医師に相談しましょう。
観察期間中、医師の指示を守ることで、治療効果を得られる可能性が高まります。
5.保険適用に基づいた費用で支払う
通常の自由診療では全額自己負担となりますが、保険が認められた場合は自己負担は原則3割(年齢や所得により1〜2割の場合もあります)で済みます。
支払額は症例や治療内容によって変動するため、治療前に見積もりを確認しておくと安心です。
また、矯正治療は長期にわたり、通院ごとに会計が発生するのが一般的です。
そのため、毎回発行される領収書は必ず保管しておきましょう。
領収書は医療費控除の申告時に必要になるだけでなく、支払いの証明書類としても重要です。
ファイルや封筒に年月順で整理しておくと、確定申告の際にスムーズに対応できます。
電子領収書を発行している医院では、データを削除せず安全な場所に保存しておくことも大切です。
参考:厚生労働省「医療費の自己負担」
短期矯正で保険適用されない4つのケース
短期矯正は、すべての症例に保険が適用されるわけではありません。
適用外のケースを理解しておかないと、あとになって予想以上の費用がかかる可能性があります。
ここでは、保険適用されない4つの症例を整理しました。
- ・見た目の改善が目的である
- ・軽度の歯並びの乱れや出っ歯(上顎前突)を治療する
- ・成人後の矯正で咬合機能に問題がない
- ・保険適用外の装置や治療法である
それぞれ見ていきましょう。
見た目の改善が目的である
歯並びを整えて見た目をよくしたいという理由だけでは、健康保険の対象にはなりません。
「前歯を揃えたい」「笑顔をきれいに見せたい」といった審美的な目的の矯正は、咀嚼や発音など機能面に大きな支障がないため、保険適用外とされています。
そのため、これらの治療はすべて自由診療で、費用は症例や方法によって、数十万円から100万円以上になることもあります。
保険適用外の矯正では、マウスピース矯正や目立ちにくい装置など選択肢が広がる一方、費用負担が大きくなる点を理解しておくことが大切です。
見た目の改善を目的とした矯正は、完全自己負担の自由診療だと認識しておきましょう。
軽度の歯並びの乱れや出っ歯(上顎前突)を治療する
歯並びが少し乱れている、あるいは前歯がやや前に出ているなどの軽度の症状は、基本的に健康保険の対象外で、費用は全額自己負担になります。
見た目の印象に影響するものの、噛む機能や発音に大きな支障を与えると判断されないためです。
なお、出っ歯や歯列の乱れが極端であっても、厚生労働省が定める特定疾患や顎変形症に該当しない限り、保険は使えないので注意しましょう。
成人後の矯正で咬合機能に問題がない
成人後に受ける矯正治療の多くは、見た目の改善や歯列を整えることを目的としています。
たとえば「前歯を揃えて見た目を整えたい」「軽度の歯列の乱れを改善したい」などは、機能的障害として判断されません。
噛み合わせに明確な異常が見られず、食事や会話に支障がない場合は、健康保険の対象外です。
このようなケースは自由診療扱いとなり、費用はすべて自己負担となります。
保険適用外の装置や治療法である
健康保険が適用される矯正治療は、基本的にワイヤーを用いた標準的な方法に限られます。
そのため、マウスピース型矯正装置(インビザラインなど)や、目立ちにくさを重視したセラミックブラケット、裏側矯正(舌側矯正)などの装置はすべて自由診療です。
これらは見た目や快適性に優れる一方、費用は全額自己負担で、症例によっては数十万円から100万円以上かかる場合もあります。
装置の種類を重視して選ぶ場合は、制度の対象外になる点を理解しておきましょう。
短期矯正の費用を抑えるコツ
短期矯正は比較的期間が短いとはいえ、自由診療の場合は高額になりやすいのが実情です。
費用を抑える工夫を知っておくことが、治療を前向きに検討するうえで大きな助けになります。
ここでは、費用を抑えるための代表的な方法を4つ紹介します。
- ・複数の歯科医院で見積もりを取る
- ・部分矯正や簡易的な治療法を検討する
- ・医療費控除を利用する
- ・デンタルローンを活用する
それぞれ活用を検討してください。
複数の歯科医院で見積もりを取る
矯正治療は自由診療となるケースが多く、医院ごとに治療方針や装置の種類、費用体系が大きく異なります。
そのため、必ず複数の医院で見積もりを比較することが大切です。
まずは初診相談を予約し、口腔内の検査や診断を受けることで、治療計画と概算費用を提示してもらえます。
その際には総額だけでなく「装置代」「調整料」「通院ごとの費用」などの内訳を確認すると安心です。
見積もりは1か所に絞らず2~3医院から取り寄せ、費用と治療内容に納得したうえで選びましょう。
また、保険適用が可能な症例であっても、医院によって取り扱いが異なるため、事前に確認しておくと安心です。
質問リストを用意しておけば、条件を効率的に比較できます。
部分矯正や簡易的な治療法を検討する
全体矯正では数十万円から100万円以上かかることがありますが、自由診療の中でも部分矯正や簡易的な治療法を選ぶことで、費用を抑えられる場合があります。
部分矯正は前歯や一部の歯だけを動かす方法で、治療期間が比較的短く、総額も30万〜50万円前後に収まることが多い傾向です。
また、軽度の歯並びの乱れであれば、簡易的なワイヤー装置やマウスピース装置で改善されるケースもあります。
ただし、これらはすべて保険適用外で、適応できる症例も限られます。
自己判断ではなく医師の診断を受け、自分の症状に合った治療範囲を選択することで、費用を節約しながら効果を得られるでしょう。
関連記事:部分矯正で起こりがちな8つのリスクとは?後悔しないための対策も紹介
医療費控除を利用する
短期矯正の費用は、条件を満たせば医療費控除の対象となり、所得税の還付を受けられる可能性があります。
医療費控除は1年間に支払った医療費が10万円を超える場合、または総所得金額が200万円未満の方は、その5%を超える場合に利用できます。
家族分を合算して申告することも可能です。
ただし、対象となるのは、咀嚼や発音の改善など機能回復を目的とした矯正治療で、審美目的のみの矯正は含まれません。
申告の際は歯科医院から受け取る領収書を大切に保管し、確定申告で明細書に記入して提出します。
制度を正しく活用すれば、数万円単位で税金の負担を軽減できるでしょう。
参考:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
デンタルローンを活用する
デンタルローンとは、矯正やインプラントなど、自由診療の歯科治療費を分割で支払える医療専用のローンです。
高額になりやすい矯正費用を一度に負担せず、毎月一定額で計画的に支払えるのが大きなメリットです。
金利はクレジットカードの分割払いより低めに設定されていることが多く、長期的に返済計画を立てるのに向いています。
ただし、利用には金融機関による審査が必要で、金利負担が発生する点を理解しておくことが大切です。
また、治療目的であれば医療費控除の対象として扱える場合もあるため、領収書は必ず保管しておきましょう。
まとまった費用をすぐに用意できない場合でも、デンタルローンを活用すれば無理なく治療を始められます。
短期矯正の保険適用でよくある質問
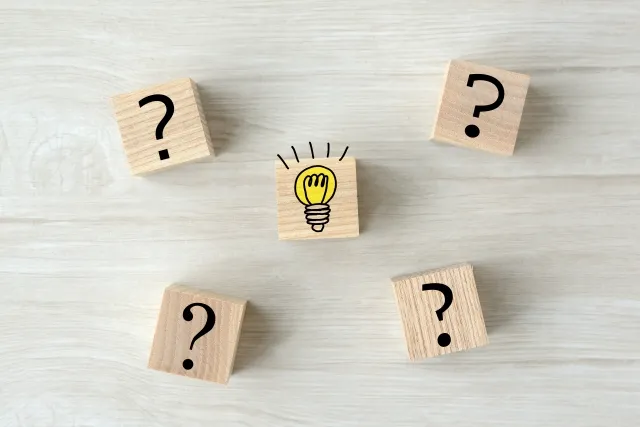
保険制度の仕組みは複雑に感じられますが、ポイントを整理しておけば安心して治療を検討できます。
ここではよく寄せられる質問を紹介します。
- ・保険適用される年齢に制限はある?
- ・保険適用される医院はどのように探せばよい?
それぞれ参考にしてください。
保険適用される年齢に制限はある?
矯正治療の保険適用は、明確に「何歳まで」といった年齢制限は設けられていません。
症例が厚生労働省の定める適用条件に該当するかどうかで判断されます。
ただし、顎の発育に合わせて効果的に治療できるケースも多いため、子どものうちに診断を受けておくと選択肢が広がる可能性があります。
保険適用される医院はどのように探せばよい?
厚生労働省から「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)」として認定されている医院かどうかを確認しましょう。
公式リストは厚生労働省や各自治体のホームページで公開されており、大学病院や矯正歯科専門の医療機関が多く含まれます。
また、地域の一般歯科で相談した場合でも、必要に応じて提携先の病院や大学病院を紹介してもらえるケースがあります。
参考:東京都福祉局「指定自立支援医療機関の情報提供(育成医療・更生医療)」
短期矯正は保険適用範囲を理解して活用しましょう
短期矯正は、先天的な異常や外傷による歯列不正、顎変形症など機能改善を目的とする場合に保険が適用されます。
適用を受けるには診断から申請、治療開始までの手順を正しく踏むことが重要です。
一方、見た目を整えるだけの治療や軽度の歯並び矯正は対象外で、自由診療として全額自己負担になります。
また、複数医院での見積もり比較や医療費控除の活用など、費用を抑える工夫も欠かせません。
制度の仕組みを理解しておけば、負担を減らしながら安心して治療を進められます。
表参道にあるMori Dental Clinicでは、短期矯正に力を入れており、目立ちにくい治療法にも対応しています。
一人ひとりに合ったプランを提案し、プライバシーに配慮した環境で安心して治療を受けられる点も魅力です。
矯正を検討している方は、まずは無料カウンセリングでお気軽にご相談ください。
監修者

森 健
Mori Dental Clinic 院長
<略歴>
- 2008年3月 明海大学歯学部卒業
- 2008年4月〜2009年3月 明海大学病院勤務
- 2009年4月〜2017年7月 都内歯科医院勤務
- 2017年9月〜 Mori Dental Clinic開院


