差し歯があってもマウスピース矯正はできる?両立のための注意点
1. マウスピース矯正と差し歯の関係とは?
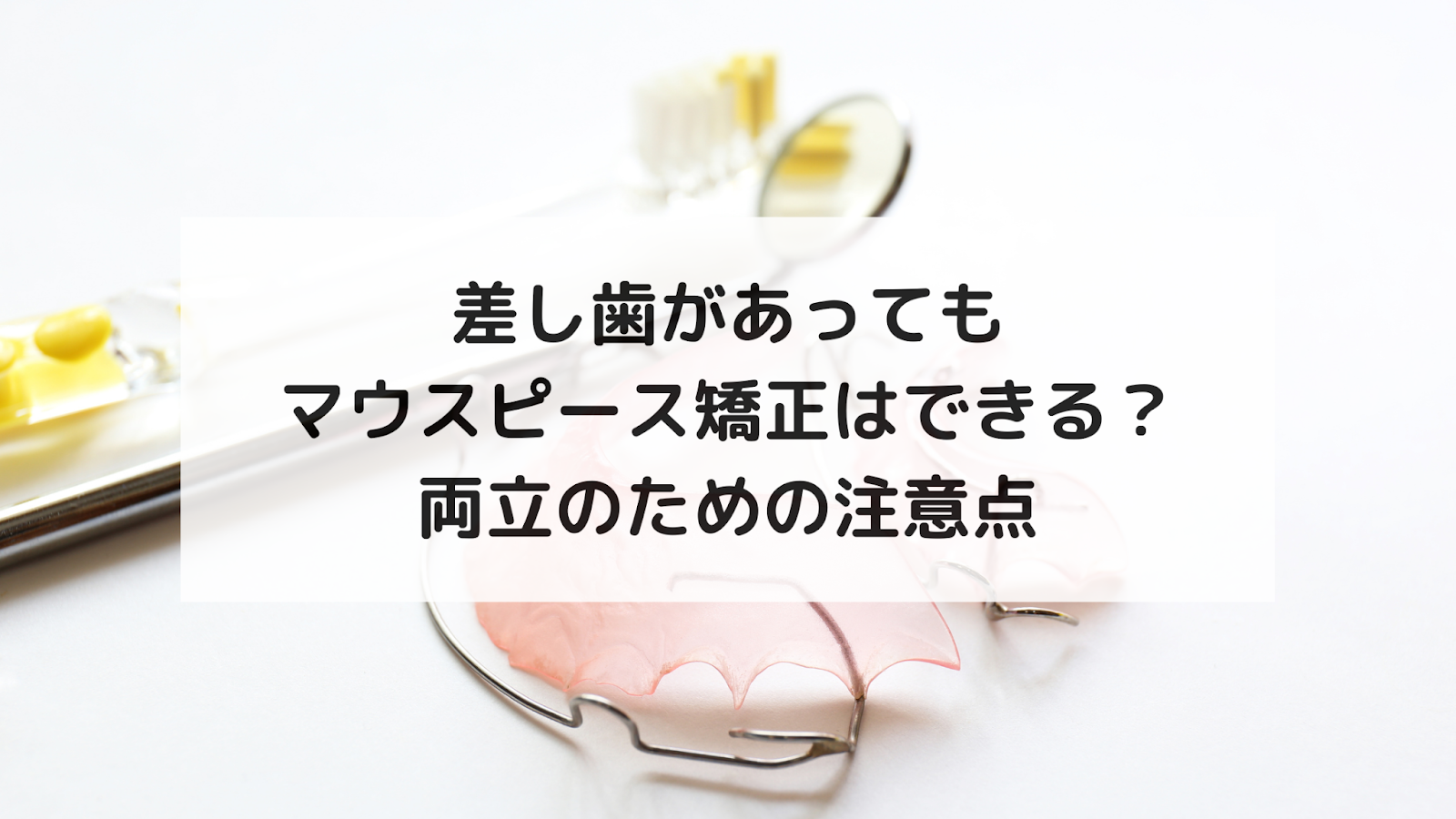
1.1 マウスピース矯正とは?
マウスピース矯正とは、透明なマウスピースを使って歯並びを整える矯正方法です。
ワイヤー矯正とは違い、目立ちにくく、取り外しができるのが大きな特徴です。最近では「インビザライン」などのマウスピース矯正が人気を集めています。
マウスピース矯正の仕組み
マウスピース矯正は、歯の動きを計算しながら、数週間ごとに新しいマウスピースに交換することで少しずつ歯を動かしていきます。
基本的な流れは以下のとおりです。
1.カウンセリング・検査:歯型を取り、矯正計画を作成
2.マウスピース作製:オーダーメイドのマウスピースを作る
3.装着開始:1日20時間以上装着し、数週間ごとに交換
4.調整・経過観察:定期的に歯科医院でチェック
5.矯正完了・保定:動かした歯を安定させるためのリテーナーを装着
マウスピース矯正の特徴
マウスピース矯正には、次のような特徴があります。
・目立たない:透明なので周囲に気づかれにくい
・取り外しができる:食事や歯磨きのときに外せる
・痛みが少ない:ワイヤー矯正よりも痛みが軽減される
・虫歯になりにくい:取り外して歯磨きできるため、衛生的
一方で、1日20時間以上の装着が必要 であり、装着時間が短いと効果が出にくくなるので注意が必要です。

1.2 差し歯とは?
差し歯とは、虫歯や外傷などで歯を失った際に、人工の歯を被せる治療方法のことです。 歯の根が残っている場合、その部分に土台を作り、その上に人工の歯を装着します。見た目が自然で、機能的にも自分の歯とほぼ変わらず使えるのが特徴です。
差し歯は、大きく分けて2種類あります。1つ目は保険適用の差し歯で、素材はレジン(プラスチック)や金属を使用。2つ目は自由診療の差し歯で、セラミックやジルコニアなどの審美性に優れた素材を使います。 保険適用のものは費用が抑えられますが、経年劣化しやすいのがデメリット。一方、自由診療の差し歯は、耐久性が高く、色や質感が自然なので、前歯など目立つ部分に向いています。
差し歯の治療は、まず虫歯や損傷した歯を削り、歯の根を残した状態にします。その後、土台となる「コア」を作り、人工の歯を装着して完成です。治療期間は、歯の状態や使用する素材によって異なりますが、通常2〜3回の通院で終わることが多いです。
差し歯のメリットは、見た目が自然で、噛む機能も回復できること。 ただし、歯の根が弱っていると、差し歯が取れたり、根が折れたりするリスクもあります。また、マウスピース矯正をする場合、差し歯がどのように影響するのかを事前に確認することが大切です。
1.3 マウスピース矯正中に差し歯があるとどうなる?
マウスピース矯正は基本的に差し歯があっても可能ですが、いくつか注意点があります。 差し歯の状態や素材によっては、矯正の計画を工夫する必要があるため、事前に歯科医師としっかり相談することが大切です。
まず、マウスピース矯正は「歯の根」を動かして歯並びを整える治療です。しかし、差し歯自体は人工の歯のため動きません。 そのため、矯正で歯を動かす際には、土台となる歯根の状態が重要になります。
差し歯がある場合の主な影響
1.歯の動きに制限が出る可能性がある
差し歯の根の状態によっては、マウスピース矯正の計画を調整する必要があります。特に、差し歯の本数が多い場合、思い通りに歯を動かしにくくなることがあります。
2.差し歯が矯正中に合わなくなることがある
矯正で歯の位置が変わると、差し歯の形や噛み合わせが合わなくなることがあります。 そのため、場合によっては矯正後に差し歯を作り直すことが必要です。
3.マウスピースがしっかりフィットしない可能性
差し歯の形が特殊だったり、大きかったりすると、マウスピースがしっかりフィットしないことがあります。 その場合、マウスピースを作る際に工夫が必要になります。
差し歯があっても矯正を成功させるポイント
差し歯がある場合、以下のポイントを意識すると、マウスピース矯正をスムーズに進めやすくなります。
・矯正前に歯の状態をしっかりチェックする
歯根の健康状態を確認し、矯正が可能かどうかを判断します。
・必要に応じて差し歯を作り直す計画を立てる
矯正後に新しい差し歯に交換することを前提に治療を進めるケースもあります。
・マウスピースのフィット感を定期的にチェックする
矯正が進むにつれてフィット感が変わることがあるため、違和感があればすぐに歯科医に相談しましょう。
差し歯があってもマウスピース矯正は可能ですが、事前の準備と計画が重要です。 矯正を検討している方は、歯科医院でしっかり相談しながら進めるのがおすすめです。
2. マウスピース矯正の差し歯への影響

2.1 差し歯の種類と矯正への影響
差し歯にはいくつかの種類があり、それぞれマウスピース矯正への影響が異なります。 素材や構造によって、矯正中の歯の動きやマウスピースのフィット感に違いが出るため、事前に確認しておくことが大切です。
主な差し歯の種類と特徴
1.レジン前装冠(保険適用)
・プラスチック(レジン)と金属でできた差し歯
・比較的安価だが、経年劣化しやすい
・強度があるが、摩耗や変色のリスクがある
2.オールセラミック(自由診療)
・すべてセラミックで作られた差し歯
・自然な見た目で変色しにくい
・強度が高く、金属アレルギーの心配がない
3.メタルボンド(自由診療)
・金属のフレームにセラミックを焼き付けたもの
・強度が高く、奥歯にも使用しやすい
・見た目は自然だが、金属アレルギーのリスクがある
4.ジルコニアクラウン(自由診療)
・高強度のジルコニアを使用した差し歯
・割れにくく、奥歯にも適している
・見た目が自然で耐久性も高い
差し歯の種類によるマウスピース矯正への影響
マウスピース矯正では、歯の根の動きが重要 になります。そのため、差し歯の種類によって、矯正のしやすさが変わることがあります。
・レジン前装冠やメタルボンドの差し歯は、矯正中に摩耗や変形の可能性があるため注意が必要です。
・オールセラミックやジルコニアは強度が高いため、矯正による影響は少ないですが、噛み合わせの変化には対応が必要です。
・マウスピースの適合性を高めるために、矯正後に差し歯を作り直すケースもあります。
どのタイプの差し歯でも、矯正中に問題が出ないように、歯科医としっかり相談しながら進めることが大切です。 矯正前に差し歯を交換するべきか、矯正後に作り直すべきかを判断し、最適な治療計画を立てましょう。
2.2 差し歯があるとマウスピース矯正はできない?
差し歯があってもマウスピース矯正は可能ですが、歯の状態によっては注意が必要です。 矯正は歯の根を動かす治療のため、差し歯自体は動きません。しかし、根の状態が良好であれば、矯正を進めることができます。
矯正が可能なケース
・差し歯が1~2本程度で、歯根がしっかりしている場合
・差し歯が奥歯にあり、前歯の歯並びを整えたい場合
・差し歯の位置に大きな矯正の負担がかからない場合
このようなケースでは、マウスピース矯正を問題なく進められることが多いです。
矯正が難しいケース
一方で、次のようなケースでは慎重な判断が必要になります。
- ・差し歯の本数が多く、歯根が弱い場合
→ 差し歯の数が多いと、動かせる歯が限られ、希望の歯並びにならない可能性があります。 - ・差し歯の土台が短く、ぐらついている場合
→ 矯正の力によって歯根に負担がかかり、歯の寿命を縮めるリスクがあります。 - ・矯正後に噛み合わせのズレが生じる可能性が高い場合
→ 差し歯の形が現在の噛み合わせに合わせて作られているため、矯正後に合わなくなることがあります。
矯正を成功させるためのポイント
差し歯がある状態でマウスピース矯正をする場合、以下の点を意識するとスムーズに進めやすくなります。
1.矯正前に歯根の状態を確認する
→ レントゲンやCTで歯根の健康状態をチェックし、矯正が可能か診断してもらいましょう。
2.矯正後に差し歯を作り直す計画を立てる
→ 歯並びが変わることで、差し歯の形や噛み合わせが合わなくなることがあるため、必要に応じて作り直しを考えておくと安心です。
3.矯正中のトラブルに対応できる歯科医院を選ぶ
→ 矯正専門のクリニックではなく、一般歯科と矯正歯科の両方を扱っている歯科医院なら、差し歯と矯正のバランスを考えた治療が受けられます。
差し歯があっても矯正できるケースは多いですが、歯の状態に応じた慎重な判断が必要です。 矯正を検討している方は、まずは歯科医院でしっかり相談してみましょう。
2.3 差し歯を作り直す必要はある?
マウスピース矯正をすると、歯の位置が変わるため、矯正前に作った差し歯が合わなくなることがあります。 そのため、矯正の前後で差し歯を作り直す必要が出てくるケースがあります。
差し歯を作り直す必要があるケース
1.矯正後に噛み合わせが変わる場合
・差し歯は現在の噛み合わせに合わせて作られています。矯正によって歯の位置が変わると、噛み合わせが合わなくなり、違和感が出ることがあります。
2.差し歯の形が歯並びに合わなくなる場合
・歯並びが整うことで、隣の歯とのバランスが変わり、差し歯の大きさや角度が合わなくなることがあります。特に前歯の差し歯は、見た目にも影響しやすいため、作り直しが必要になることが多いです。
3.矯正中にマウスピースがフィットしにくくなる場合
・差し歯の形状によっては、マウスピースがしっかりフィットしないことがあります。その場合、矯正の途中で差し歯を仮歯に変更し、矯正が終わった後に最終的な差し歯を作る方法をとることがあります。
作り直しが不要なケース
すべての差し歯が作り直しになるわけではありません。以下のようなケースでは、矯正後もそのまま使用できることがあります。
・矯正の影響を受けにくい奥歯の差し歯
・前歯の矯正が中心で、奥歯の差し歯に大きな影響がない場合は、作り直しの必要がないこともあります。
・すでに矯正後の歯並びを考慮して作られた差し歯
・矯正を見越して作られた差し歯であれば、矯正後にも違和感なく使えることがあります。
差し歯を作り直すタイミング
差し歯の作り直しは、矯正の前にするべきか、後にするべきかで悩む方が多いです。それぞれのメリット・デメリットを見てみましょう。
・矯正前に作り直す場合
・メリット:矯正中の見た目が気にならない
・デメリット:矯正後に再調整が必要になる可能性がある
・矯正後に作り直す場合(おすすめ)
・メリット:矯正後の歯並びにピッタリ合った差し歯が作れる
・デメリット:矯正中に仮歯を使うことがある
基本的には、矯正が完了してから差し歯を作り直す方が、噛み合わせや見た目のバランスを考えやすく、おすすめです。 ただし、矯正中に仮歯が必要になることもあるため、事前に歯科医としっかり相談しましょう。
3. マウスピース矯正と差し歯のトラブル対策

3.1 マウスピースがフィットしない場合の対処法
マウスピース矯正では、しっかりフィットしないと歯が予定通りに動かず、矯正の効果が出にくくなります。 特に差し歯がある場合、マウスピースが浮いたりズレたりすることがあるため、適切な対処が必要です。
マウスピースがフィットしない原因
マウスピースがうまくはまらない原因はいくつか考えられます。
1.装着時間が不足している
・1日20時間以上装着しないと、歯が正しく動かず、マウスピースが合わなくなることがあります。
2.差し歯の形が影響している
・差し歯が大きかったり、特殊な形をしていたりすると、マウスピースが正しくフィットしないことがあります。
3.新しいマウスピースに交換したばかり
・交換直後は少しキツく感じることが多いですが、数日で馴染むことがほとんどです。
4.歯が予定通りに動いていない
・矯正計画と実際の歯の動きにズレが生じると、次のマウスピースがはまりにくくなります。
マウスピースがフィットしないときの対処法
もしマウスピースがしっかりはまらない場合、次の方法を試してみましょう。
1.シリコン製のチューイーを使う
・マウスピースをしっかりフィットさせるための専用アイテム「チューイー」を噛むと、より密着しやすくなります。
2.装着時間を見直す
・20時間以上しっかり装着できているか再確認しましょう。特に食事や歯磨き後に装着を忘れないことが大切です。
3.マウスピースを温める
・ぬるま湯(40℃以下)に数秒つけると、少し柔らかくなりフィットしやすくなることがあります。ただし、熱湯は変形の原因になるため避けましょう。
4..無理に押し込まない
・フィットしないからといって強く押し込むと、マウスピースが破損したり、歯に余計な負担がかかったりすることがあります。無理に押し込まず、違和感が続く場合は歯科医に相談しましょう。
5.歯科医院で調整してもらう
・何日経ってもフィットしない場合、歯の動きが計画通りに進んでいない可能性があります。歯科医に相談し、調整が必要か確認しましょう。
マウスピースが合わないまま放置すると、矯正計画がずれてしまう可能性があります。違和感を感じたら、早めに対処することが大切です。
3.2 マウスピース矯正前に差し歯を作り直すべきケース
差し歯がある状態でマウスピース矯正を始める場合、先に差し歯を作り直したほうがよいケースがあります。 これは、矯正中や矯正後に噛み合わせや歯並びが大きく変わる可能性があるためです。では、どんな場合に矯正前の作り直しが必要になるのか、具体的に見ていきましょう。
矯正前に差し歯を作り直すべきケース
1.現在の差し歯が古く、劣化している場合
・差し歯の素材によっては、長年の使用で変色したり、すり減ったりすることがあります。矯正中に破損する可能性があるため、劣化が進んでいる場合は、先に新しくするのが安心です。
2.差し歯のサイズや形が矯正の妨げになる場合
・差し歯の大きさや形が特殊で、マウスピースの適合を妨げることがあります。例えば、通常より大きい差し歯があると、マウスピースが正しくはまらないことがあります。この場合は、矯正前に形を調整することが推奨されます。
3.差し歯の土台(歯根)の状態が悪い場合
・差し歯の根元(支えている天然の歯)が虫歯や炎症を起こしていると、矯正中にトラブルが発生する可能性があります。特に、根の治療が必要な場合は、矯正を始める前に対応しておくべきです。
4.噛み合わせに問題があり、矯正後の形が大きく変わる場合
・差し歯は、現在の噛み合わせに合わせて作られています。そのため、矯正によって噛み合わせが変わると、差し歯の形が合わなくなることがあります。大きな噛み合わせのズレがある場合、矯正前に仮歯にしておくことを検討しましょう。
5.前歯の差し歯で、審美性を重視したい場合
・前歯の差し歯は見た目に大きく影響するため、矯正後の理想的な歯並びに合わせて作るのがベストです。矯正前に仮歯を作り、矯正が完了した後に最終的な差し歯を作る方法もあります。
矯正前に差し歯を作り直す場合の流れ
差し歯を作り直すときは、次のような流れで進めるのが一般的です。
1.矯正前の診察で、差し歯の状態をチェック
・レントゲンや口腔内検査で、歯根の状態や噛み合わせを確認します。
2.必要に応じて、仮歯に変更する
・矯正中に形が変わる可能性がある場合、仮歯を使って様子を見ることもあります。
3.矯正後に最終的な差し歯を作る
・矯正完了後に噛み合わせを確認し、理想的な形の差し歯を作製します。
矯正前に差し歯を作り直すべきかどうかは、歯の状態や矯正計画によって異なります。 無駄な治療を避けるためにも、歯科医院でしっかり相談しながら判断することが大切です。
3.3 マウスピース矯正後の差し歯の再調整
マウスピース矯正が完了すると、歯並びや噛み合わせが変わるため、差し歯の再調整が必要になることがあります。 特に前歯や噛み合わせに関わる差し歯は、矯正後に違和感が出やすいため、適切な調整を行うことが大切です。
矯正後に差し歯を再調整する理由
1.噛み合わせが変わるため
・矯正前に比べて歯の位置が変わると、今までの差し歯の高さや角度が合わなくなることがあります。違和感を放置すると、噛みにくさや顎への負担につながるため、必要に応じて調整が必要です。
2.歯の間のすき間や段差ができることがあるため
・差し歯は元の歯並びに合わせて作られているため、矯正後に微妙なすき間や段差ができることがあります。見た目や噛み心地を改善するために、作り直しを検討することもあります。
3.差し歯の色や形が合わなくなる場合があるため
・矯正によって歯の位置が変わると、差し歯のサイズや形が不自然に見えることがあります。特に前歯の差し歯は目立ちやすいため、より自然な仕上がりにするために再調整が必要になることがあります。
差し歯の再調整の方法
1. 噛み合わせの微調整
矯正後に噛み合わせが変わった場合、差し歯の表面を少し削ることで高さを調整することができます。ただし、大きく削ると差し歯の耐久性が下がるため、慎重な調整が必要です。
2. 差し歯の形を修正する
すき間や段差が気になる場合、歯科用の樹脂を使って形を整えることができます。これにより、自然な見た目と噛みやすさを維持できます。
3. 差し歯を新しく作り直す
矯正後の歯並びに完全にフィットさせるために、差し歯を作り直すこともあります。特に審美性が求められる前歯の場合、新しい差し歯を作ることで、より自然で美しい仕上がりになります。
矯正後の差し歯再調整のタイミング
矯正が完了した直後に差し歯を作り直すのではなく、一定期間リテーナー(保定装置)を使用し、歯が安定してから再調整するのが理想的です。 目安としては、矯正完了後3~6ヶ月ほど経ってから、差し歯の再調整を行うのが一般的です。
矯正後に違和感があれば、放置せずに歯科医院で相談し、適切な調整を行いましょう。
4. マウスピース矯正と差し歯のメリット・デメリット
4.1 マウスピース矯正のメリット・デメリット
マウスピース矯正は、透明なマウスピースを使って歯並びを整える矯正方法です。 見た目が自然で痛みが少ないという特徴がありますが、一方でデメリットもあるため、自分に合っているかしっかり確認することが大切です。
マウスピース矯正のメリット
1.目立ちにくい
・透明なマウスピースを使用するため、ワイヤー矯正に比べて目立ちません。人と話す機会が多い方や、見た目を気にする方に向いています。
2.取り外しができる
・食事や歯磨きの際に取り外せるため、口腔内を清潔に保ちやすいです。ワイヤー矯正のように食べ物が詰まりにくく、虫歯のリスクも抑えられます。
3.痛みが少ない
・ワイヤー矯正のように金属が口内に当たって傷つくことがなく、比較的痛みが少ないです。歯が移動する際の圧力も緩やかで、ストレスなく矯正を進められます。
4.金属アレルギーの心配がない
・金属を使用しないため、アレルギーのある方でも安心して使用できます。
5.通院回数が少ない
・ワイヤー矯正は1ヶ月に1回程度の調整が必要ですが、マウスピース矯正は2〜3ヶ月に1回のチェックで済むことが多く、忙しい方にも適しています。
マウスピース矯正のデメリット
1.装着時間を守らないと効果が出にくい
・1日20時間以上装着しないと、計画通りに歯が動かず、矯正期間が延びる可能性があります。自己管理が苦手な方には向いていないかもしれません。
2.歯並びによっては適応できない場合がある
・大きなズレや噛み合わせの問題がある場合、マウスピース矯正では対応が難しく、ワイヤー矯正のほうが適していることもあります。
3.食事や飲み物の制限がある
・マウスピースを装着したまま飲めるのは基本的に水だけです。着色しやすい飲み物(コーヒー、紅茶、ワインなど)や糖分を含む飲み物を摂取すると、マウスピースが汚れたり、虫歯のリスクが上がったりするため、注意が必要です。
4.費用が比較的高い
・保険適用外のため、ワイヤー矯正と比べて費用が高くなることがあります。治療プランによりますが、総額で50万~100万円ほどかかることが多いです。
5.マウスピースの管理が必要
・紛失や破損を防ぐために、しっかり管理する必要があります。また、装着する前に歯を磨かないと、マウスピースの中で虫歯が進行するリスクがあるため、こまめなケアが求められます。
マウスピース矯正はこんな人におすすめ!
・矯正中の見た目を気にせず、目立たない方法を選びたい方
・自分でしっかり装着時間を管理できる方
・金属アレルギーがある方
・通院回数を少なくしたい方
・軽度~中度の歯並びの乱れを治したい方
マウスピース矯正には多くのメリットがありますが、デメリットも理解したうえで、自分に合った矯正方法を選ぶことが大切です。 矯正を検討している方は、歯科医院で詳しく相談してみましょう。
4.2 差し歯のメリット・デメリット
差し歯は、虫歯や外傷などで歯を失った際に、人工の歯を装着する治療法です。 自然な見た目を保ちつつ、しっかり噛めるようになるため、機能性と審美性を両立できるのが特徴です。しかし、差し歯にもメリットとデメリットがあるため、事前にしっかり理解しておくことが大切です。
差し歯のメリット
1.見た目が自然で美しい
・セラミックやジルコニアなどの素材を選べば、自分の歯とほぼ同じ色や質感を再現できます。特に前歯の治療では、審美性を重視した差し歯が人気です。
2.しっかり噛める
・抜歯後にそのまま放置すると、噛み合わせが悪くなったり、隣の歯が傾いたりすることがありますが、差し歯を入れることで噛む機能を回復できます。
3.比較的短期間で治療が完了する
・差し歯の治療は、通常2~3回の通院で完了します。インプラント治療のように長期間の治療が必要ないため、すぐに噛む機能を取り戻したい方に適しています。
4.歯並びを整えることができる
・ある程度の歯並びの乱れであれば、差し歯の形や角度を調整することで、見た目をきれいにすることができます。
5.金属アレルギーの心配がない(メタルフリーの場合)
・オールセラミックやジルコニアの差し歯を選べば、金属アレルギーの心配がありません。
差し歯のデメリット
1.歯を削る必要がある
・差し歯を作るためには、土台となる歯を削らなければなりません。健康な歯を削ることになるため、慎重な判断が必要です。
2.差し歯の寿命がある
・永久に使えるわけではなく、素材によっては10年ほどで交換が必要になることがあります。特に保険適用のレジン製の差し歯は、変色や摩耗が早いため、早めの交換が必要です。
.3.噛み合わせによっては割れたり外れたりすることがある
・差し歯は天然の歯よりも強度が弱い場合があり、強い力がかかると割れたり外れたりすることがあります。特に奥歯の場合、食いしばりや歯ぎしりによってダメージを受けやすいです。
4.保険適用の素材は審美性が劣る
・保険適用のレジン前装冠(プラスチック製の差し歯)は、時間が経つと変色しやすく、見た目の美しさが長持ちしません。長期間きれいな状態を維持したい場合は、自由診療のセラミックやジルコニアを選ぶ必要があります。
5.矯正の際に影響を受ける可能性がある
・差し歯は天然の歯と違って動かすことができないため、マウスピース矯正をする際に影響が出ることがあります。噛み合わせが変わると、矯正後に差し歯を作り直す必要が出てくることもあります。
差し歯が向いている人は?
・虫歯やケガで歯の大部分を失った人
・短期間でしっかり噛めるようになりたい人
・前歯の見た目を美しくしたい人
・矯正をせずに歯並びをある程度整えたい人
差し歯は、審美性と機能性を兼ね備えた治療法ですが、寿命や噛み合わせの影響も考慮する必要があります。 長く快適に使うためには、定期的なメンテナンスや、歯科医との相談が大切です。
4.3 差し歯があってもマウスピース矯正を成功させるには
差し歯があってもマウスピース矯正は可能ですが、成功させるためにはいくつかのポイントを押さえておくことが大切です。 差し歯の位置や状態によって、矯正の進め方や仕上がりが変わるため、事前にしっかり計画を立てることが重要になります。
1. 矯正前に歯の状態をしっかりチェックする
まず、矯正を始める前に歯根の状態や噛み合わせをチェックすることが必須です。差し歯があっても、土台となる歯の根がしっかりしていれば、問題なく矯正できます。しかし、歯根が弱っている場合は、矯正の力がかかることでトラブルが発生する可能性があります。
矯正前に歯科医院でレントゲンやCTを撮影し、歯根や骨の状態を確認しておきましょう。
2. 差し歯の作り直しが必要か確認する
矯正後に噛み合わせが変わると、差し歯の形やサイズが合わなくなる可能性があります。そのため、事前に矯正後のプランを確認し、差し歯の作り直しが必要かどうか相談しておくことが大切です。
矯正後に作り直すべきか、矯正前に仮歯にしておくべきかは、歯の状態や矯正の進め方によって変わります。歯科医と相談しながら、最適なタイミングを決めましょう。
3. マウスピースのフィット感を確認する
差し歯の形によっては、マウスピースがしっかりフィットしないことがあります。 特に、差し歯が大きかったり特殊な形をしていたりすると、マウスピースが浮いてしまうことがあります。
マウスピースを装着した際に違和感がある場合は、専用のチューイー(シリコン製の噛むアイテム)を使ってしっかりフィットさせることが大切です。それでも合わない場合は、歯科医に相談して調整してもらいましょう。
4. 装着時間を守り、しっかり管理する
マウスピース矯正は、1日20時間以上の装着が推奨されています。 しかし、差し歯がある場合、しっかりフィットしていないと歯が予定通りに動かないことがあります。
特に、装着時間が短くなると、歯の移動が計画通りに進まず、矯正期間が長引く可能性があるため注意が必要です。食事や歯磨きの際には取り外せますが、それ以外の時間はできるだけ装着するよう心がけましょう。
5. 矯正後の保定(リテーナー)をしっかり行う
矯正が完了した後は、歯が元の位置に戻らないように保定装置(リテーナー)を装着することが重要です。差し歯がある場合、矯正前の噛み合わせに戻ろうとする力が働きやすいため、保定期間をしっかり守ることが大切です。
リテーナーの種類には、固定式と取り外し式があります。差し歯がある場合は、取り外し式のリテーナーのほうが適していることが多いですが、どちらが良いかは歯科医と相談して決めましょう。
6. 差し歯と矯正の両方に対応できる歯科医院を選ぶ
矯正と差し歯の調整は、それぞれ専門的な技術が必要です。そのため、矯正専門のクリニックではなく、一般歯科と矯正歯科の両方を扱っている歯科医院を選ぶと安心です。 そうすることで、矯正と差し歯のバランスを考えた治療を受けることができます。
5. まとめ:マウスピース矯正と差し歯を両立するには
差し歯があってもマウスピース矯正は可能ですが、成功させるためにはいくつかのポイントを押さえることが大切です。 差し歯の状態や矯正の計画をしっかり考え、適切な対応をすることで、理想の歯並びと噛み合わせを手に入れることができます。
マウスピース矯正と差し歯を両立するためのポイント
1.矯正前に歯根や噛み合わせをチェックする
・レントゲンやCTを撮影し、差し歯の土台となる歯根の状態を確認しましょう。
2.矯正後に差し歯を作り直す計画を立てる
・矯正によって噛み合わせが変わるため、必要に応じて新しい差し歯に交換することを考えておきましょう。
3.マウスピースのフィット感をこまめにチェックする
・差し歯の形によってはマウスピースが浮くことがあるため、違和感を感じたら歯科医に相談しましょう。
4.装着時間を守り、矯正計画に従う
・1日20時間以上の装着を心がけ、マウスピースを正しく使いましょう。
5.矯正後の保定をしっかり行う
・リテーナーを適切に使用し、せっかく整えた歯並びを安定させましょう。
6.矯正と差し歯の両方に対応できる歯科医院を選ぶ
・差し歯と矯正のバランスを考えた治療を受けるために、経験豊富な歯科医がいるクリニックを選びましょう。
マウスピース矯正と差し歯は、適切な計画と管理をすれば両立が可能です。 矯正を検討している方は、歯科医としっかり相談しながら、最適な治療プランを立てることが成功への鍵となります。
理想の歯並びを手に入れ、快適な毎日を送りましょう!
マウスピース矯正なら森デンタルクリニックへ!
マウスピース矯正を考えているけれど、「差し歯があるけど大丈夫?」「矯正後に差し歯を作り直すべき?」 など、不安を感じていませんか?
森デンタルクリニックでは、矯正治療と一般歯科の両方に対応しているため、差し歯がある方のマウスピース矯正も安心してお任せいただけます。 お一人おひとりの歯の状態に合わせた治療計画を立て、理想の歯並びへと導きます。
矯正や差し歯に関するお悩みは、ぜひ森デンタルクリニックにご相談ください!
まずは無料カウンセリングで、お気軽にお問い合わせを♪



